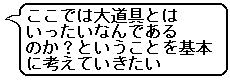教授は『舞台装置』という言葉を役者が演じる舞台を形作る装置という意味だと考えているからである。 そのまんまではあるが。 舞台を形作ると言えば照明や音、小道具などもそうである。 では大道具と小道具の違いはなんであろうか?
大別すると名前の通り大きいものと小さいものになるが、それは舞台の背景となっているものかそうでないかであるからだと思う。
例えば勉強机があるとする。するとそこはだれかの勉強部屋だ!とわかる。 しかし、参考書だけおいてあってもそこが図書館なのかそれともごみ捨て場に捨ててあるのかはわからない。 背景とはこういうことなのである。
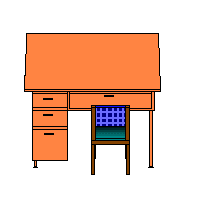 |
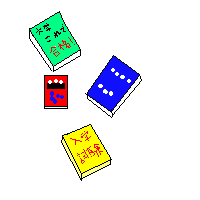 |
| ここは誰かの部屋だ。 | ここは?ゴミ捨て場か? |
しかし、系統として2種類にわけることができる。具象系と抽象系である。 この2つにはどのような違いがあるのだろうか。絵を考えてもらえばわかりやすいと思う。抽象系の舞台は何かを抽象的に表した 形である。これは1つの物事を抽象的に表す場合と多くの物を1つの形に見たてて使いまわしのようにする場合がある。 具象系はそのまま。実際と同じようなものをつくる。
しかし、この区分はあまり覚える必要はない。要は自分たちがどのような舞台を作りたいか、によるのである。
具体的な例を挙げるとすれば、演劇集団キャラメルボックスが結構抽象的であると思われる。(ほんのいくつかしか見てないのに言うのもなんだが)また、劇団扉座(関東圏ではけっこう有名)がかなり具象的であると思う。(こっちもほんのいくつかしか見てないのに言うのもなんだ が) これじゃなんの説明にもなっていないじゃないですか!(謀忍弦)。 わ、わかっておる。
では、どういうことが大道具のプランを作るのに必要かというと。
| 1.まず脚本をしっかり読みこむ。 | これは普通でもあたりまえのことですが。しかし、しっかりと読みこんで自分のイメージを作る。 ここはこういう装置がいいのでは?とか。こういう装置をつくったら効率的じゃないか。とか。要は自分の作りたいように作れば良い。 |
| 2.いろいろ試行錯誤 | イメージができたら、実際の置きかた、大きさを考える。この時実物と同じ縮尺で考えることが基本。 簡単な模型(ダンボールとかで)をつくるとさらにわかりやすい。 |
| 3.みんなと相談 | どうするか決め兼ねたら相談してみよう。もっといいアイディアが出るかもしれないし、大道具は他分野と密接に関わるからだ。 |