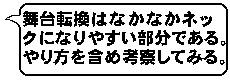1.なぜ転換するのか
まあ当たり前の理由ではあるが、舞台背景などを客に分かりやすいように随時組み替えたいからである。 2.転換の基本
転換するにあたっては大概暗転を使うことになるだろう。すると、あまりに長い時間暗転していると、客の心が芝居から離れてしまうなどの弊害がおきてくる。音響で音楽をながすなどの工夫はできるが、やはり、作業時間をいかに短くするかが大きな課題になってくるだろう。そのためには、効率の良い組み方、人数が必要になってくるのは間違いない。
また、舞台上にいる人数は限られてくるのでその辺りも考慮に入れる必要があると思う。
また全ての道具を全部入れ替えるのもいいが、置き場所や人数を考えると舞台上にあるもので変形などさせていくと、時間的な面でも転換しやすくなると思う。
転換する際には乱暴な言い方をすれば「客から見えなければいい」という面がある。まぁ、舞台裏などもそう言えるが。つまり、効率よく転換するには、見えない部分にいかに上手く転換させる要素を組み込めるか、ということなのかもしれない。 3.例-1:パズル
 |
様々な形の装置をパズルのように組み替えて形を作っていくやり方。左図は6個のならんだ椅子をベッドへ組み替えていく様。もちろん人数がいれば同時進行は可能。 |
 |
ある部分ないし一部分を蝶番で固定し、折りたたんで大きさを変えていくという方法。左図はテーブルをコタツに組み替えていく様子。まずはテーブルクロスをはずし、天板をはずす。次に足を折って下におき、最後にコタツ布団をかぶせ、天板を戻せば完成。 |
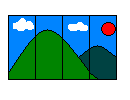 |
衝立(パネル)に蝶番を使って、もう一枚動かせる部分をくっつけて、その裏表の絵を変え、動かすことで舞台を転換します。 |
ストーリーによっては登場人物が物を出し入れしたり、あるいは黒子がそれをしたりという工夫も盛り込める。
例えば、演劇部の話だったとすれば、劇の進行をさせるために転換も見せてしまうというのがあげられるだろう。 また、薄暗くしてわざと見せて(2000年高校演劇全国大会「男でしょ!」など)デザイン性などを出す手法も考えられる。