
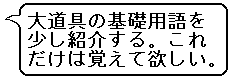 どの大道具関係の本を見ても最初にこれがあると思います。
どの大道具関係の本を見ても最初にこれがあると思います。| ナグリ | いわゆる金槌や木槌のこと。ただし、一般的には金槌をさす。 ガンガンなぐるように打つことから由来しているのではないだろうか。 普通平らな面と少し出っ張っている2種類の面を持っているが、普通は平らな面で打ち、最後の決めで出っ張っているほうを使う。 コツ よけいな力を抜き、手首のスナップだけで打つとズレない。 また、金槌が目標に当たった瞬間に押し付けるように止める。 物をたたくと反動で跳ね返されてしまうが、その跳ね返しが起きないように押し付ける。 また、打つ部分から遠いトコロを持った方がより強く打てる。 |
| ノコ | 鋸(のこぎり)のことである。両刃の物とそうでないものがあるが、どちらでもかまわないと思う。 普通、刃の細かい方を木目とはそわない方向に、刃の荒い方を木目にそって使う。 コツ 日本のノコは肩の力を抜いてひく時に力を入れる。切る時につける印は2面、もしくは3面につけると上手く切れる。 ある程度の高さの水平な場所で切る。安全のため必ず靴をはき、しっかりと足で切るものを押さえる。 |
| 罫書 | けがき。けがく。ノコで切る場所に印をつけたりすること。 これを失敗するとメチャクチャなものになってしまうので注意! コツ とにかく集中!細かいところまでみなければだめ。長い場合コンマ1度でもづれると大変。 |
| 曲金 | 直角に曲がった定規。罫書をしたり、木材などの直角を測ったりする。 ちゃんとしたものを作るには必須のアイテム。 |
| 釘 | くぎ。近年長さはミリであらわされている。 長さは基本的に打ち込む対象の3分の2以上うまるくらいの長さもしくは貼る板の厚さの3倍以上なら 釘が簡単に抜けることはない。 また、角材同士を打つときは釘は2本打つ。釘が1本では角材が回ってしまうからである。 あと、少し斜めに打つと釘が抜けにくいのでじょうぶになる。 19ミリ、50ミリ、65ミリの3種類があればたりるであろう。 |
| メジャー | 曲金より長いものを測ったりすうときに使う。2人がかりで安定したところでやるとよい。4m 以上のものがあると便利だ。測る時には必ず直角に合わせる。 |
| バール | 一般的に言う釘抜き。ナグリとセットで使うことが多い。 コツ 自分の体重が一番かけやすいように使うと釘が抜けやすい。テコの原理を使っているのでなるべくはしっこを持つ。 |
| 人形立て | 人形とも言う。パネルや張物を立てるときに使う。詳しい作り方は大道具編4の方に。 |
| 金やすり | 金属のやすり。木工用と金属用がある。 木工用では金属はけすれないし金属用では木材は削れないので買うといきには注意。 また、かなり神経を使って削らないと妙な形に削れてしまうので安易に使わないほうが良いと思う。 コツ同じ方向にけずるときれいにけづることができる。 |
| 舞台図面 | 装置の図面。立面図や平面図などある。詳しくはリンクの方へ! |
| サンドペーパー | 紙やすりとも言う。仕上げなどに使う。目の粗いものから順番にかけていくことが大切である。 コツ 上の金やすりと同じように同じ方向にけづる。角材にまくと使いやすい。 |
| 工具カッター | 普通のカッターではなく、工具用の大きなカッター。ベニヤを切るときなどに使う。 曲がらないように切ることが大切である。安全に使う使い方はリンクの方をみてほしい。 |
| 尺貫法 | 昔から日本にある長さの単位。今でも舞台ではこえが使われているので覚えていないと大変である。 詳しくはリンクの方に書く。 |
| 木材 | ベニヤ・角材など。ベニヤは薄い合板。角材は普通の木を四角くカットしたもの。(これはわかるか・・・) |
| パネル | ベニヤと角材でつくるもの。いろいろ応用できる。詳しくはパネルを作る編で。 |
| 平台 | パネルの応用版。ただし、これは人が乗れるくらいじょうぶである。 |
| 山台 | 規格外サイズの平台。 |
| 箱馬 | 箱馬。箱足。高さをつくったりするもの。平台と組み合わせることが多い。 |
| 高足 | 箱馬の脚立のような形のバージョン。こっちのほうが簡単だが、その分安定性にかけるようだ。 |
| けこみ | 大道具で平台を箱馬などで高くしたときなどに隙間をかくしたり、そこにデザインをつけたりするもの。 これがないと結構みっともなかったりする。 |